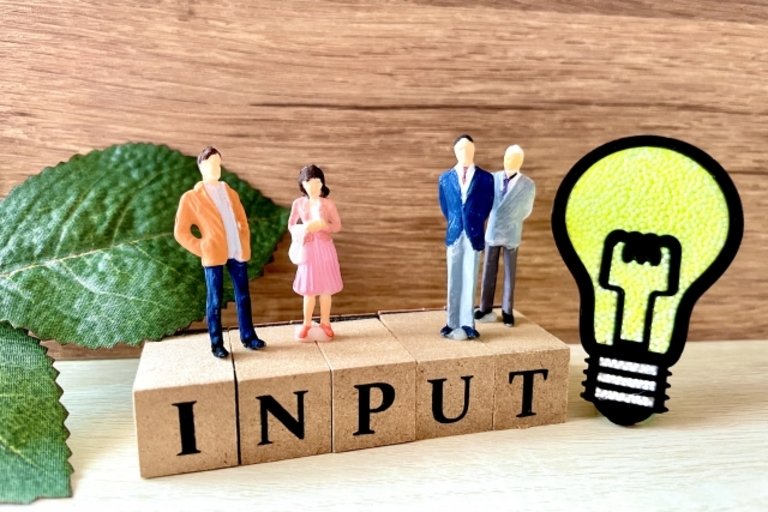こんにちは!ライターの【もか】です!
私は社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得し、2年ほど就労継続支援B型(以下、B型事業所)で、障害のある方の作業補助や製品の検品などをしていました。
ライターに転身してから早2年。
B型事業所で働いていた頃の体験を記事に盛り込むこともあるのですが、記憶があいまいになっていたり、制度がガラッと変わっていたりすることも珍しくありません。
そんなときは、さまざまな手段を使ってよりリアルな情報をインプットしています。
今回は、福祉の現場を離れた私が、普段どのようにリアルな情報を手に入れているのか解説します!
①SNSを見る
1番手っ取り早く情報を入手する方法が「SNSを見ること」です。
検索窓にキーワードを入れるだけで、関連する投稿がずらーっと出てきます。
SNSのメリットは、今まさに福祉職として働いている方の「ぶっちゃけた話」が聞ける点です。
とくにX(旧Twitter)は、現場で働いていて不満に思っていることや、「この制度ってどうなの?」といった疑問など、普段は言いづらい福祉職の本音が垣間見えます。
一方で、SNSには誤った情報や極端に偏った意見が混ざっている場合も少なくありません。
情報を取得する際には、「あくまで個人の意見」ということを念頭に置いておく必要があります。
②関連書籍を買って読む
SNSの次に手軽な方法が「関連書籍を買って読むこと」です。
書店や通販で気になっているテーマの本を買って読む、シンプルな方法です。
図書館で本を借りる方法もありますが、私はあえて本を買って読んでいます。
図書館で借りた本には、参考になる情報があっても印を付けられないからです。
私が最近買った本は、八木亜希子氏の【相談援助職の「伝わる記録」現場で使える実践事例74】です。
この本を購入した理由は、障害福祉サービスの実地指導に関する記事を書いているときに、「具体的にどんな支援記録だと実地指導に引っかかるのだろう?」と思ったからです。
インターネットで検索しても、障害福祉サービスの支援記録の記載例が掲載されたページがみつからなかったため、購入しました。
本を購入するのは少々お金と手間がかかりますが、執筆者の名前が記載されている分、信頼性のある情報を入手できます。
③福祉業界で働いている友人から話を聞く
ここからは、実際に福祉業界で働いている人から話を聞く方法を紹介します。
その第1歩として使えるのが「福祉業界で働いている友人から話を聞く」方法です。
幸い私の友人は今でも病院や支援施設などで働いている人が多いため、「最近仕事どんな感じ?」といったノリで話を聞けます。
ただの世間話でも、現場で働いているからこそリアルな話が聞ける場合もあるのです。
例えば、私がこの日報を書いている1ヵ月前に友人と会ったときは、「私たち、もう社会人5年目の27歳だけど、転職したらだいたい1番若くない!?」という話題で盛り上がりました。
実際に、2023年度の調査によると「福祉業界で働く人の約半数が就職から3年未満で退職している」というデータもあります。
このように数値で示すのもよいですが、「社会人5年目の27歳が転職すると、多くの場合は年齢・経歴ともに一番若い職員になる」と聞くと、より情報にリアリティが増したのではないでしょうか。
④インタビューをする
実際に福祉業界で働いている人から話を聞く方法として外せないのが「インタビュー」です。
友人との世間話のノリで話を聞くのではなく、きちんとアポイントメントをとってインタビュアーの方にお話を聞きます。
私がデジタルレトリバーのライターとして、初めてインタビューさせていただいたときは、以下のような質問をしました。
- Q.処遇改善加算を取得したことによって、実際に働いている職員の方のお給料が上がったり、職場環境に変化があったりしましたか?
- Q.令和6年度の報酬改定によって処遇改善加算が一本化されましたが、実際に事務負担が減ったり、加算額が増えたりしましたか?
このように、インタビュアーの方の体験談を引き出す質問をすると、より情報にリアリティを持たせられます。
⑤福祉職が集まる大会や学会に参加する
リアルな情報をインプットする方法として、社会福祉士や精神保健福祉士が集まる大会や学会に参加する方法もあります。
私は1ヵ月前に「第60回日本精神保健福祉士協会全国大会」のプレ企画に参加しました。
プレ企画では、全国から集まってきた精神保健福祉士が日々の支援業務で感じている課題について話し合いました。
さまざまな意見が飛び交うなか、私が特に印象に残ったのは以下のとおりです。
- 支援者のメンタルヘルスに対するペイが少ない
- 福祉職の給料保障など立場の保証!
- (支援員が)高齢化すると若い職員が離れていく
- 働きやすい職場は空気が良い!
- 書類多いわ!!
この企画に参加して、「利用者さんに対する支援のあり方と同じくらい、福祉職の立場や職場環境に関する悩みを抱えている人が多いな」と実感しました。
友人に誘われて参加した大会でしたが、逆に参加しなければ、ここまでリアルな声は聞けていなかったと思います。
AIが書いた文章にリアリティを持たせるには?
ここまでさまざまなインプット術を紹介してきましたが、すべて文章の内容にリアリティを持たせる目的があります。
キーワードに関する情報を文章にまとめる作業はAIに任せられます。
しかし、AIが出した情報が本当に正しいかどうかを判断したり、実際に経験した情報を盛り込んだりするのは人間にしかできません。(少なくとも現段階では)
とくに医療・福祉に関する記事は、記事を読んでいる人の生活に大きな影響を与える可能性があるため、よりリアルな情報を記事に盛り込む必要があります。
これからも正確でリアルな情報を届けるため、私はインプットし続けます。