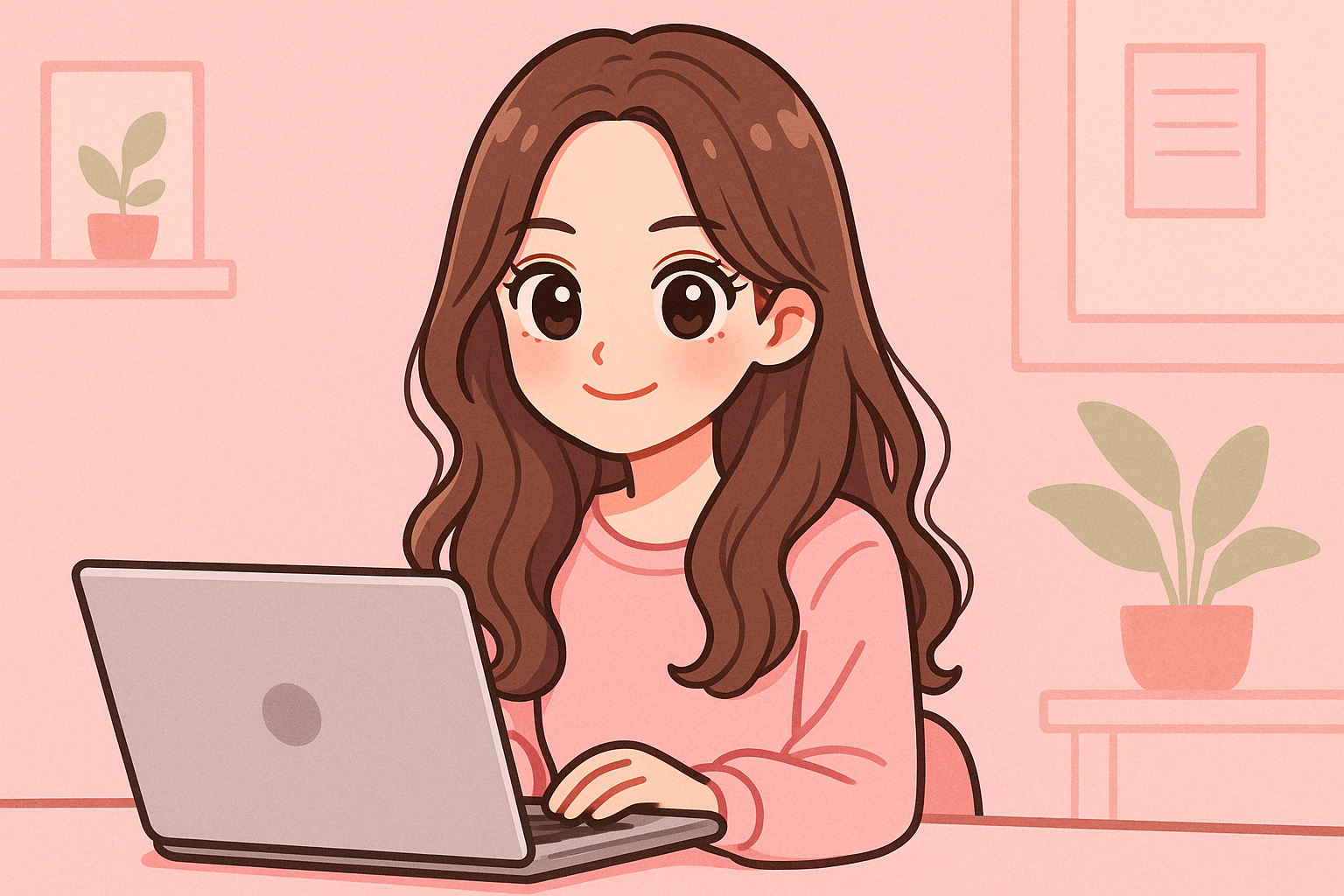こんにちは、SEOライターのまるもっちゃんです。
ライターとして執筆を始めたのが、2年前。
企業に勤めはじめた当時は、右も左もわからなかった私ですが、2年間で200記事以上作成してきた上で強く感じたのは、文章は知識だけじゃ届かないということ。
今回の記事では、情報があふれる時代にあえて“温度”をのせる理由、読者の共感を引き出す4つのこだわり、最近の執筆で感じたリアルな気づき、さらにSEOをベースにしながらも心に届く文章に仕上げる工夫までご紹介します。
読み終わったあとに「まるもっちゃんの書いた記事、他にも読んでみたいな」と思ってもらえたら本望です。
情報はあふれているのに、足りないもの

ここ最近は、相談したいことがあっても生身の人に聞くのではなく、ChatGPTがまるで友達みたいに寄り添って話を聞いてくれる時代。
さらに、正論や正しい情報を知りたいだけなら、人に聞かなくても検索すれば一瞬で答えが出てきますよね。
元々接客業をしていた私からすると、少し寂しい時代だなと感じることもあります。
でも同時に、便利なAIやチャットサービスのおかげで、誰もが簡単に答えを見つけられるようになったのも事実です。
だからこそ私が記事を書くときに大切にしているのは、文字に乗せて私が知っている知識や感じたことを読者の皆さんと共感し、対話するように想いを乗せて執筆しています。
記事までたどり着いてくれる方は、本当にその情報を知りたくて、わざわざ記事やコラムを読みに来てくれているはず。
その背景を想うだけで、自然とやる気がみなぎってきます。
ちなみに、余談ですが筆者のMBTIはENFP。明るく社交的で、好奇心旺盛。新しいものや面白そうなテーマを見つけると、つい夢中になって調べてしまうタイプです。
その“勢い”や“熱量”は、記事づくりのときにも活かされています。
リサーチや構成を進めるときは、ワクワクしながら深掘りしていくので、書きながら「こんな切り口もある!」と新しい発想が生まれることも。
知識や経験をただ並べるのではなく、読者が「自分ごと」として受け取れるように届けたい。
そんな気持ちをこれからも文章に込めていきたいと思っています。
文章に「私らしさ」を込める4つのこだわり
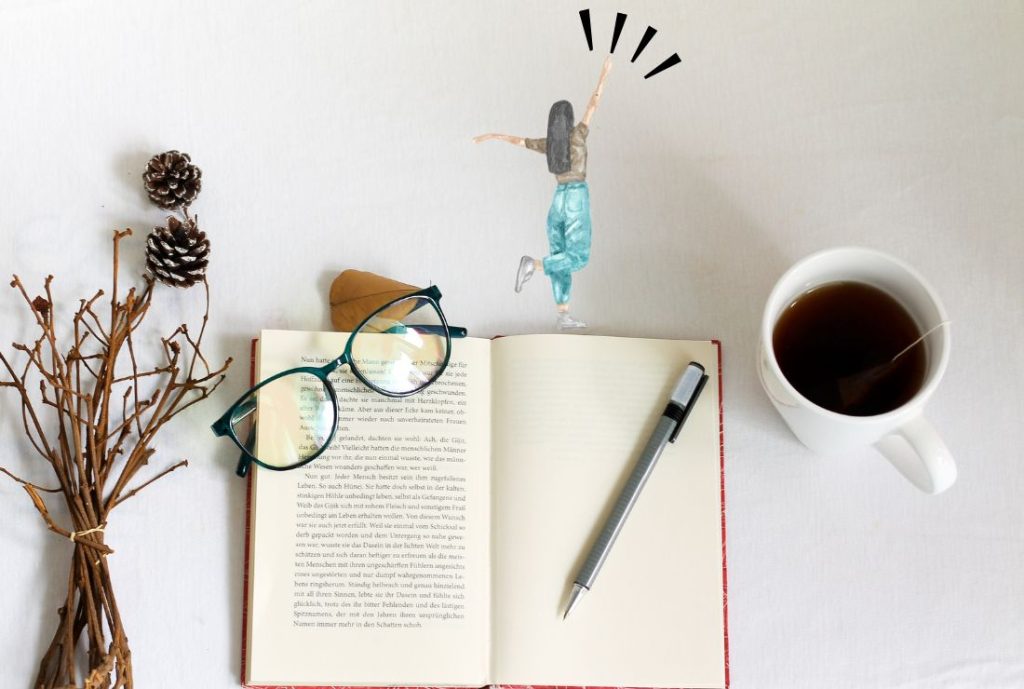
記事を執筆するときに、文章に「私らしさ」を込める4つのこだわりがあります。
① 読みやすく・わかりやすい文章にする
② ノリとテンションで共感力を刺激する
③ 実体験を取り入れて知識や経験をシェア
④ 読者の気持ちに寄り添う
ここからは、この4つのこだわりについて、具体的にご紹介します。
①読みやすく・わかりやすい文章にする
専門用語をそのまま並べると、読者が「ん?結局どういうこと?」と置いてけぼりになってしまいます。だから私は、できるだけわかりやすい文章で伝えるようにしています。
実は、私は、ライターをする前にコンサルとして雇われたのですが、全くの初心者で、社内で飛び交う会話の専門用語を覚えるのに、苦労しました。
たとえば、いちばん最初につまずいたのが「CVR」と「CTR」という言葉。アルファベットの略語ばかりで、「わけわからん!」と思ったのを今でも覚えています(笑)
記事を読み進めるうえでは、私と同じように専門用語に戸惑った読者が置いてけぼりにならないように、以下のような工夫をしています。
・CVR(コンバージョン率)
意味は、クリックして記事やサイトに来た人が、最終的に目的の行動(会員登録・資料請求・購入など)をした割合。
つまり、記事を読みに来てくれた人のうち、どれだけが「よし、登録してみよう!」「このサービスいいかも」と実際にアクションを起こしてくれたかを数字で表しています。
| 計算式:実際に登録した数 ÷ きてくれた数 × 100(%) |
・CTR(クリック率)
意味は、広告や検索結果が表示された回数のうち、どれだけクリックされたかを表す数字。
つまり、記事や広告が表示されたときに、「なんか気になる!」と思ってクリックしてもらえた割合を指します。
| 計算式:クリックした数 ÷ 表示された回数 × 100(%) |
このように書き換えます。このようにイメージしやすい言葉に変換することで、読者がスッとイメージできるように変換するのが、私のこだわりです。
②ノリとテンションで共感力を刺激する
読者が「うわー、これめっちゃわかる!」と読みながら頷きすぎて、気づいたら首もげてたわ。と思うくらいの共感力を刺激したいのです(笑)だから、記事の中には必ず「あるある」や「そうそう!」と頷ける一文を入れるようにしています。
真剣なテーマでも、ノリやテンションを少しだけ混ぜることで、堅苦しくない読者と同じ空気感を生み出せるのです。
③実体験を取り入れて知識や経験をシェア
「ただの情報」ではなく、「あ、この人も同じ気持ちになったことあるんだ」と思ってもらえること。これを大切にしています。
自分の体験や感じたことを書くことで、読者は「自分だけじゃなかった」と安心できます。
たとえば婚活での迷いも、過去の自分を重ねて書くことで、情報だけでは届かない温度が生まれるのです。
④読者の気持ちに寄り添う
私はあくまでも、答えを押しつける立場にはなりたくありません。
「これが正解です!」と決めつけるより、「一緒に考えてみませんか?」というスタンスで書くことで、読者も肩の力を抜いて読み進められますし、「相談してもいいかも」と思えるような安心感を届けられると考えています。
正直、正論や正しい知識なんて検索すればすぐに出てきます。
だからこそ私の記事は「知識+温度」で届けたい。読んだ人が「情報を知れてよかった」だけでなく「気持ちが軽くなった」と感じてもらえることを目指しています。
最近の執筆から感じたこと

文章を書くたびに、「読者はどんな気持ちでこの記事を探してくれたんだろう?」と考えることがあります。
最近執筆した記事の中で、個人的に一番気になったし、書きながら「面白いテーマだな」と思えたのが「既読スルーの男性心理とは?脈あり・脈なしの見極めと正しい対処法」という記事です。
恋愛や婚活の現場では多くの人が悩むテーマで、検索する人も多いテーマだということもあり、心理学的な知見やデータを並べるだけなら簡単ですが、それだけでは本当に伝えたいことには届かないと個人的に感じました。
書き進める中で気づいたのは、情報や心理パターンだけを羅列する執筆にはしたくないということ。
形式的な対処法ではなく、「私はあなたのモヤモヤに寄り添いたい」という気持ちを、文章を通して届けたかったのです。
そこで意識したのが、データと一緒に“体験の温度”を伝えること。過去の自分が抱えていた迷いや不安を素直に重ね合わせ、「あのときの私も同じ気持ちだった」と書き添えました。
すると記事全体がやわらかくなり、ただの情報ではなく、“寄り添う文章”へと変わったように思います。
もちろんSEOの工夫も忘れていません。「既読スルー 男性心理 脈あり 脈なし」といった検索意図に応えるキーワードはきちんと取り入れました。ただ、それはあくまでベース。
この記事を公開したあと、実際に、私がライターだと知っている友人からもLINEが来て「ねえ、これ私のこと書いたでしょ!?笑」なんて言われました。もちろんそんなつもりはなかったのですが…(笑)
身近な人からそんな感想をもらえたのは、情報を超えてそれくらい“自分ごと”として“気持ち”が伝わった証拠だと思っています。
本当に大切なのは、記事を読んでくれた人が「この文章、私の気持ちを考えてくれている」と感じてくれることだと、改めて実感しました。
ベースのSEOで意識しているこだわり
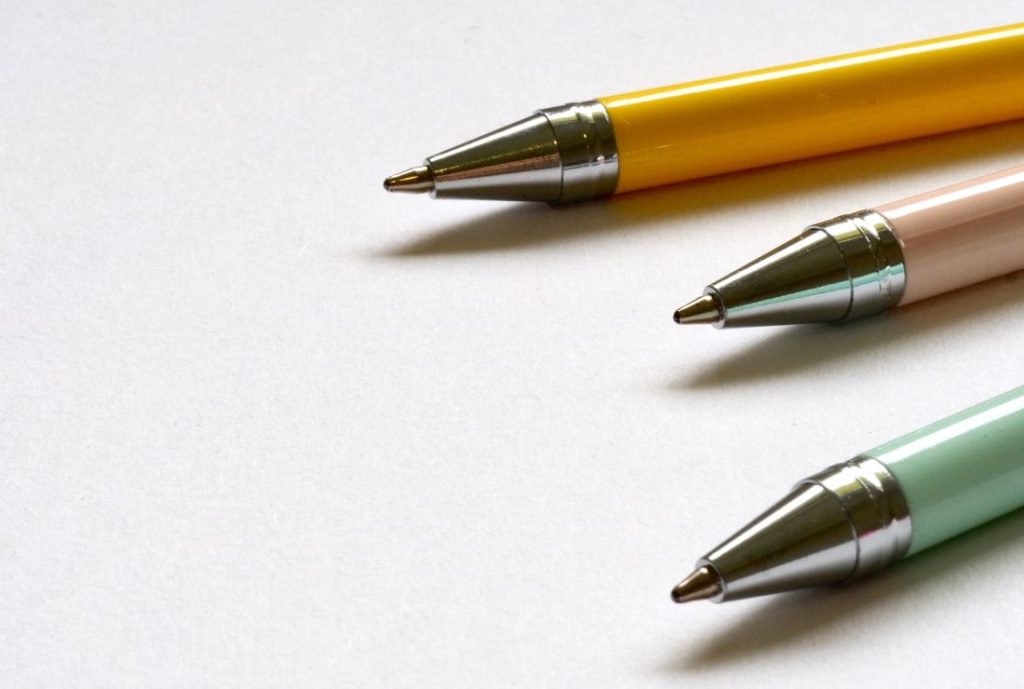
もちろん、ライターとしてSEOのことも大事にしています。記事はただ書くだけではなく、「この言葉を調べている人は、どんな不安や期待を抱えているのか」を想像しながら作成することを大切にしています。
顕在ニーズと潜在ニーズ
そのためにまず意識しているのが、顕在ニーズと潜在ニーズ。
先ほどの記事を例に出しますが「既読スルー 男性心理」と検索する人は、
・「彼の本音を知りたい」という表向きのニーズ(顕在ニーズ)
・「この関係は脈あり?脈なし?」という裏側の不安(潜在ニーズ)
を同時に抱えています。
私は記事を作成する際、こうした二層のニーズを満たせるように構成を組み立てています。
また、どうやって検索してこの記事にたどり着くのかまで想定したうえで、
ここからさらに具体的に想像します。
| 具体的な想像例 「気になる男性から既読スルーされているかも…」と不安になった20代前半〜30代前半の女性が、夜にスマホで「男性 既読スルー」と検索する。そこで結婚相談所のオウンドメディア記事を見つけ、「専門家の視点で詳しい心理が書いてありそう」と期待して読みに来てくれるページ。 |
ここまで読者の状況をイメージしたうえで、導入から結論までの流れを設計しています。
キーワード選定
キーワードを選ぶときも感覚では決めません。
ラッコキーワードを使って関連語を洗い出し、競合記事を分析して「どの言葉に需要が集まっているか」をチェックします。
さらに、自分のオウンドメディアではGoogleサーチコンソールのデータも参考にして、実際に検索されているワードを記事に反映させています。
こうして選んだキーワードを自然に記事に散りばめつつ、見出しで答えを提示したり、情報を段階的に並べたりすることで、読者が最後までスムーズに読めることを意識しています。
SEOはあくまで地図のようなもの。地図がなければ目的地に着けませんが、旅を楽しくするのは人との会話や出会いです。
記事も同じで、キーワードや構成は基盤にすぎません。最終的に読者の心を動かすのは、人の言葉だと信じています。
だから私は、「検索でたどり着いた」だけで終わらせず、「読んでよかった」と思ってもらえる記事を書く。そのために、温度や共感を一番大切にしています。
これからも“人に届く文章”を書いていきたい

ちょっと仕事のこだわり部分は、真面目な文章になってしまったかもしれませんが、いかがだったでしょうか?
私は知識や経験を出し惜しみせず、読者と同じ目線で考えられる文章を書きたいと思っています。
記事を通して「ちょっと前向きになれた」と感じてもらえたら、それが最高の喜びです。
この日誌でも、執筆の裏側や日常の小さな気づきを交えながら、共感と知識をお届けしていきたいです。最後まで読んでいただきありがとうございました。